内縁者に財産を相続させる4つの方法
遺言、養子縁組など
婚姻届を提出して正式に結婚しているわけではありませんが、実質的に夫婦と同様に生計を共にしている関係を内縁と呼ぶことがあります。
内縁関係にある方は、どれだけ親密な関係を築いていたとしても、残念ながらどちらか一方が亡くなった場合にその方の財産を相続する権利はありません。
ただし、前もって準備をしておくことで、死後に財産を譲り渡す方法がいくつかあります。
ここではその概要をご説明致します。
内縁者同士で養子縁組をする

ちょっと奇抜な方法ではありますが、内縁者同士が養子縁組をして、親子としてあらたな親族関係を創設することで、相続を可能にする方法があります。
養子縁組は、一方を養親、もう一方を養子として役所に届出を行うだけで成立します。
参考ページ:内縁者や養子の相続分
養子となった方は、養親となった方が亡くなった際は子供として当然に相続人となります。
また養子となった方自身に子供がいない場合であれば、養親も直系尊属として相続人となることが出来ます。
夫婦という認識で過ごしていた方同士が、あらためて親子となるというのは不思議ですが、将来的な財産の承継だけを考えれば有効な手段の一つです。
もっとも、この方法が万能というわけでありません。年下の方が養親となることは出来ないことや、養子となった方は姓が変わることになること、他にも実子や養子がいる場合は、相続分が均等になることなどに注意が必要です。
遺言書を作成する(遺贈)

一番スタンダードな、代表的な方法が遺言書を作成することです。
遺言書に「すべての財産を○○に遺贈する」という内容を記載して作成しておけば、例え相続人ではない内縁者でも、本人が亡くなった後の財産を受け取ることが出来ます。
遺言書については下記のページを参考にしてください。
もっとも、この場合注意しなければならないのが遺留分という制度です。
もし、遺言を作成した方に、子供や戸籍上離婚していない配偶者がいるような場合は、例え全ての財産を内縁者に遺贈するという遺言が残されていたとしても、本来の相続分の半分を請求することが出来ます。
第1028条
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一
もっとも、この遺留分の問題はあくまで本人たちが請求した場合に限られており、内縁者が全て取得することに誰も異議がないようであれば、それはそれで大丈夫ということになります。
もし後から揉めることを避けたいのであれば、遺言書の作成段階から、本来の相続人に遺留分相当を取得させる内容を盛り込んでおくのも一つの手段ですが、そもそも相続人全員が遺留分を主張するかどうかはわかりません。この点はそれぞれの家庭事情や人間関係によっても変わってくるものです。
死因贈与契約

内縁者との間で、自分が死亡した場合には財産を贈与します、という契約を事前に交わしておくことが出来ます。
この契約を死因贈与といいます。
遺言との一番の違いは、遺言は当事者の一方が単独でする行為なので、後から内容を変更しても自由ですが、死因贈与は双方が合意の上締結する「契約」であるため、どちらか一方だけの判断で変更は出来ないという点です。
また、不動産について死因贈与契約を締結した場合は、登記簿に死因贈与契約をしていることを仮登記することが出来ます。
仮登記とは、簡単に言うと将来的な名義変更の予約のようなもので、それがなされていると一定の権利保全効果が得られます。
このようにメリットもありますが、亡くなった後の手続きについては相続人の協力を得なければならないケースもあり、利用されているケースは遺言に比べると多くはないのが現状です。
また、遺留分について考慮すべき内容については遺言と同様となります。
特別縁故者として家庭裁判所に財産分与を申立てる
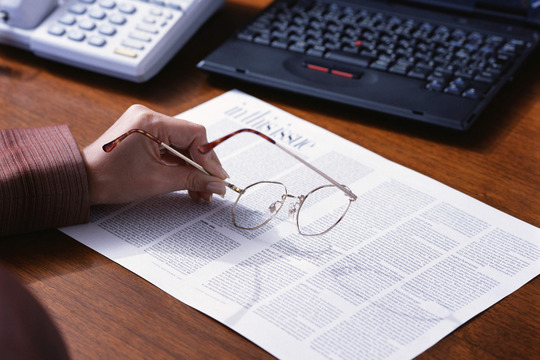
特別縁故者とは
「被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者」のことです。
民法958条の3では被相続人に相続人がいない場合に限って、上記の要件を満たした特別縁故者が家庭裁判所に対して財産の分与を請求できる旨定められています。
従って、特別縁故者に対する財産分与の申立を行なうというのが方法のひとつです。
もっとも、この申立が全面的に認められるケースは多くありません。
本人たちがどれだけ特別な縁故を主張したとしても、裁判所はとても厳格に判断をするため、なかなか認められません。
まったく分与を認められないことや、一部しか認められないことなども沢山あります。
そのため、初めからこの方法を頼りにするのは不確定要素が大きすぎて危険です。
インターネットで検索すると非常に簡単に認められそうな記事や、分与が認められた判例等が沢山見つかりますが、実際のところは否決されている事例も多いのです。
よって、この方法をアテにしてまったく対策をしないということは避け、あくまで最後の頼みの綱という認識でいた方が良いと思います。
まとめ
このように、本来相続分を持たない内縁者に対しても、死後に財産を承継させる手段はいくつかあります。
また、それぞれの手段について、メリットやデメリットがあります。
そのため、財産の内容や親族関係など、様々なことを考慮して検討する必要があります。
もし迷うようであれば、一番手軽に出来て、後でやり直しも出来る「遺言書作成」をしてみてはいかがかと思います。
遺言書作成のご相談を受け付けています。
当事務所では次のような方を対象に遺言書作成のサポートを行っています。
- 遺言書を作りたいが、どうしたら良いかわからない
- どのような内容の文書にしたらよいかわからない
- 遺言の内容についてアドバイスが欲しい
- 遺言に書きたい文章内容に問題がないかどうかチェックして欲しい
- 遺言を作るべきかどうか迷っている
- 遺言以外に良い方法がないか知りたい
LⅠN E 公式アカウントからもお問合せいただけます
LINEを使ってのお問合せも可能です。電話をする時間が中々作れないという方は是非ご活用ください。
↓↓友達登録はこちら↓↓
