遺言書のつくり方
ここでは遺言書のつくり方をご説明致します。
遺言書にも種類がある

遺言書にはいくつか種類があります。
ここでは、もっとも用いられている下記の2つの方法をご紹介致します。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場という所で手数料を払って、公文書として遺言書を作成する方法です。
自筆証書遺言とは、自分で手書きで作成する方法です。
自筆証書遺言のつくり方
要件
自筆証書遺言は紙1枚とペンが一本あれば自分で書いて作ることが出来ます。ただし、ただ思うがままに書くだけではだめで、その要件が民法で詳しく書かれています。
よくテレビドラマなどで、遺言をワープロで書いたり、ビデオにとったりするシーンを目にしますが、それらは全て、決まった要件を満たしていないので、全くの無効、意味のないものになってしまいます。
民法で定めた自筆証書遺言の要件は次のとおりです。
①全文を自筆する(※但し平成31年1月13日より要件緩和!)
②正確な日付を書く
③自筆で署名する
④自筆で住所を書く
⑤押印する
<例えばこんな遺言は全て無効になります>
・ワープロで書いた遺言
・ビデオに撮った遺言
・印鑑が押していないもの
・文字ではなく、絵や記号で表現しているもの
・暗号になっているもの
・口で伝えた内容を第三者が書き起こしたもの
・平成25年3月吉日と書いてあるもの
などなどたくさんあります。
せっかく遺言を書いたのに、もし無効になるとその内容は全く反映されない事になります。手軽に安く作れるメリットはありますが、出来る限りこの方法ではなく、公正証書遺言をお勧めします。
自筆証書遺言の記載例
遺言書

遺言者◎◎ △△は次のとおり遺言する。
一、私が所有する下記の不動産を、●●県●●市●●町●丁目●●番●号 A山B太郎が相続する。
所 在 ●●県●●市●●町●丁目
地 番 ●●番地●●
地 目 宅地
地 積 ●●.●●㎡
所 在 ●●県●●市●●町●丁目●●番地●●
家屋番号 ●●番●●
種 類 居宅
構 造 木造瓦葺二階建
床 面 積 1階 ●●.●●㎡
2階 ●●.●●㎡
二、下記の預貯金を●●県●●市●●町●丁目●●番●号 C川D子に遺贈する。
株式会社●●銀行 ●●支店
普通口座 ●●●●●●
名義 ◎◎ △△
三、上記以外の財産は全て●●県●●市●●町●丁目●●番●号 E岡F夫が相続する。
四、遺言執行者として下記の者を指定する。
住 所 ●●県●●市●●町●丁目●●番●号
氏 名 G崎I子
生年月日 昭和●●年●月●日
職 業 ●●
以上
平成●●年●●月●●日
●●県●●市●●町●丁目●●番●号
◎◎ △△
財産の記載は、自筆ではなくてもOKとなった。
平成31年1月13日より、自筆証書遺言に関する法律が少し変わりました。
今まではすべての文章をひとつ残らず自筆で書く必要がありました。
しかし民法の改正によって、預金や不動産など財産の内容についての記載は、自筆でなくとも
目録を添付すれば良いということに要件が緩和されたのです。
民法第968条第2項
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全文又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書に因らない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
いままでですと、すべて遺言者自身が書かなければならずとても大変でした。
預貯金や株はまだしも、不動産を正確に記入するには、所在、地番、地目、地積などという普段あまり使わない言葉が頻出しますし、マンションに至っては敷地権の表示やマンション名などもあるので、書かなければならない量は膨大でした。
遺言書を作成する方は高齢者が多いので、この点が非常に大変でした。
自分の名前も、手が震えて書くのに時間がかかる方たちがこれらの記載を正確に記入するのにはとても時間がかかりますし、仮に途中で1字でも間違えてしまうと、民法に沿った訂正をきちんとするか、書き直すしかありませんでした。
しかしこの改正以後は、不動産や預金の記載について別の人が代わりに書いてあげたり、パソコンで打ってプリントアウトしたものを一緒につけるという方法を取ることができるようになりました。非常に画期的な改正です。
ただし、目録自体に「署名、押印」が必要とされており、「一体のものとして」という要件も付されています。今後は「一体のものとして」という範囲がどこまでなのか、判例や見解が別れることになる部分もあると予想されます。
自筆証書遺言は「検認手続」が必要
自筆証書遺言でとても重要な事がもうひとつあります。それは、遺言者が亡くなった後に、誰かが必ず検認手続きというものを行わなければならない事です。これは、遺言書を家庭裁判所へ持っていき、このような遺言書が残されていましたという事実を裁判所に認証してもらう事で、その後の偽造や変造を防ぐ手続きです。検認手続きをする人は、遺言書を生前から保管していた方や遺言書を発見した相続人です。その方のいずれかが家庭裁判所に対し検認手続きの申立てを行うと、●月●日に検認を行うので家庭裁判所に来てください、という内容の通知が相続人全員に届きます。もし遺言書に封がされている場合はその日に開けるので、それまで中身はわかりません。
この検認手続きを行わないと、せっかく遺言書が残されていても、まったく意味のないものになってしまうので注意が必要です。
なお、詳しくは裁判所のホームページが参考になります。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_17/
結構集める書類がたくさんあります。もし、わからない場合は専門家に頼むと楽だと思います。
念のための証拠作りが大事
自筆証書遺言は第三者から見ると、本当に本人が書いたものなのかどうか全く判断できません。
その為、民法で定められている要件を満たすだけではなく出来るだけ本人が自分の意思で書いたものだという証拠を残しておいた方が良いでしょう。
具体的には次の通りです。
- 書いている最中の写真をとる
- 書き終わった遺言書を本人が手に持ち、内容が見えるように自分と一緒に撮影する。
- 実印で押印して、印鑑証明書とセットで保管する。
- 信頼できる人に写しを預けておく。
これだけのことをしておけば大分安心です。
ただし、出来れば次に紹介する公正証書遺言を作成する事をおすすめします。
公正証書遺言のつくり方
公正証書遺言とは?どのようにつくる?
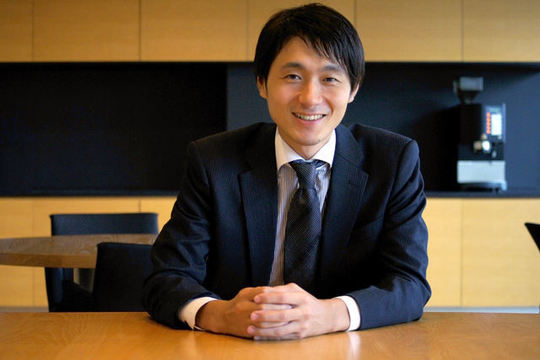
公正証書遺言とは、公証役場という役所で、公証人という方に作ってもらう遺言書の事です。公証役場はひとつの都道府県の中にいくつかあります。
首都圏だとちょっと電車に乗れば行ける場所に大体あります。イメージとしては、遺言を書く人と付き添いの方(証人)3人で公証役場へ直接行って、こういった遺言を残したいと公証人に伝えます。
それを公証人が書面に仕上げてみんなでハンコを押すといった手続きです。
公正証書遺言のメリット

特に理由がなければ、出来るだけ自筆証書遺言を避けて公正証書遺言を作成すべきです。その理由は次のとおりです。
①検認の必要がない
公証役場で第三者が作成するため、作成の段階で役所の確認が済んでしまいます。その為自筆証書遺言で必要だった家庭裁判所での検認手続きを行う必要がありません。この点は遺されたご家族にとって非常に負担が軽くなる要素です。
②公証役場に記録が保管される
誰かが後で偽造したのではないかと疑いをかけてきたり、遺言書をなくしてしまって内容が分からなくなってしまった場合も、公証役場に記録が保管されるため安心です。
③間違いが減る
公証人というプロが作るので、法的に無効だったり、住所などが間違っていたなどというミスはほとんど起こりません。
④信憑性が高い
公正証書という形で和紙の書面が作成されるため、手書きで書いた自筆証書遺言と比べても、他人が抱く信憑性度合いは段違いにあがります。財産を相続人に移すため銀行や証券会社に遺言書を提出することがありますが、公正証書だとすんなり受け入れてくれることが多いです。逆に自筆証書を持ち込むと、本物かどうか判断できないことを理由に手続きの進行を断られる事もあります。本当に本人が書いたものであるのかどうが、非常に判断が難しいのです。
LⅠN E 公式アカウントからもお問合せいただけます
LINEを使ってのお問合せも可能です。電話をする時間が中々作れないという方は是非ご活用ください。
↓↓友達登録はこちら↓↓