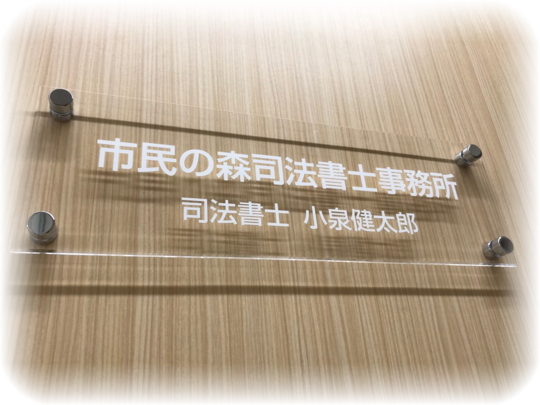借地権とは
目次
- 借地権とは
- 借地権は普通の賃借権よりもずっと強い権利
- 借地権自体は登記しないことが多い
- 建物の登記を変更すれば他人に権利を主張できる
- 譲渡には地主の承諾が必要
- 旧法借地権とは
借地権とは
借地権とは「建物の所有を目的とする地上権及び賃借権」のことで、借地借家法という法律で定められている権利です。
「借家」とか「賃貸借」など似たような用語がたくさんあり紛らわしいですが、借地権も含めてそれぞれ法律的には異なるものです。
家や土地に限らず、お金を払ってなにかを借りることを賃貸借といい、民法の条文で内容が定められています。
具体的に言うと、DVDレンタルとかレンタカーなどがそれにあたります。
(反対に、まったくお金を払わずにタダで借りることを使用貸借といいます。)
その賃貸借の中でも、対象物が「土地」であって、さらに賃貸の目的が「建物所有」である場合に限って、特に区別して定められているのが「借地権」という権利です。
借地権の相続手続きについては下記のページをどうぞ
関連ページ:「借地権を相続する方法」
借地権は、普通の賃借権よりもずっと強い権利
借地権は建物所有を目的としているため借主の保護が普通の土地の賃貸よりもずっと重要になってきます。
そのため、駐車場などとして利用するような普通の賃貸借と比べ、その権利も強いものになっています。
一番大きいのは、存続期間が長いことです。
普通の賃貸借であれば期間は契約で自由に設定することができますが、借地権の場合は最初の設定時に30年以上の期間を設けなければならないことになっています。
また、最初の更新は20年以上、2回目以降の更新は10年以上という制限もあるため、借地権者は一度建てた建物をすぐに明け渡さなければならないということはありません。
借地権自体は登記しないことが多い
通常、土地に対してなんらかの権利を取得した場合は、法務局に対してその権利の登記をすることがほとんどです。
例えば、土地の所有者になった場合は所有権移転登記を、土地を担保にとった場合は抵当権設定登記をするのが一般的です。
登記が完了すると、その内容は登記事項証明書に記載され、第三者に対してその権利を公示することで権利を正当に主張できるようになります。
そして同様に、借地権も賃借権設定登記をし、公示することが出来ます。
しかし実際は、登記をすることはあまりなく、私文書の契約書や公正証書などの書類だけで済ませているのが現状です。
建物の名義を変更すれば他人に権利を主張できる
上述のとおり、借地権はとても強い権利であるにも関わらず、登記自体行わないことが実務上とても多いです。
なぜかと言うと、借地借家法では、借地権についてはその目的である建物に所有者としての登記がなされていれば、土地の登記がなくとも第三者に対して自分が借地権者であることを主張できる旨定められているからです。
もちろん登記をすること自体はまったく問題ないのですが、登録免許税や代理人への手数料等の経費もかかるため、わざわざ登記することなく済ませることが多いのです。
(借地借家法)
第十条 借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。
譲渡には地主の承諾が必要
借地権という権利は、その権利自体を他人へ譲渡することが出来ます。
そのため、普通の土地付き一戸建てと同じように建物と一緒に中古の住宅として売却したり、親族に無償で贈与したりすることも可能です。
しかし、地主に無断で譲渡することは出来ず、きちんとその地主から承諾をもらわなければなりません。
もっとも、特段の理由もないのに地主が承諾してくれない場合は、裁判を提起して、承諾を求めることが出来ます。
また、譲渡に関しては地主に承諾料を支払うことが一般的です。
この承諾料は一般的な相場がありますが、100万円以上になることが多く、この点は所有権付物件を譲渡するときと比べると大きな経費負担となります。
旧法借地権とは
上で述べたように、借地権という権利は「借地借家法」という法律で内容が定められています。
この借地借家法という法律は実は比較的新しく制定された法律で、実際に法律が使われるようになった(施行)のは、1992年(平成4年)になります。
しかし、それまで借地権という権利が存在しなかったわけではなく、「借地法」という法律があってその法律の中でしっかりと定められていました。
「借地借家法」の借地権と「借地法」の借地権は内容が若干異なり、一般的には旧法借地権の方が借主に有利だったと言われています。
また借地借家法では、その施行以前に設定された借地権(旧法借地権)はその後もずっと継続して借地法が適用され、契約の更新がなされる限り何年たっても旧法借地権のまま使い続けることができます。
今現在、住宅として流通している借地権付一戸建ては、実は旧法借地権のものが多く、借地借家法施行後も旧法のままたくさん取引がなされています。
当事務所のお手伝い
不動産、銀行、株など、あらゆる相続のお手続きを当事務所が代行いたします。
遺産分割協議書の作成から財産の名義変更など、おまかせください。
一番多く、お申し込みがある
お手伝い内容になります。
残された財産よりも借金の方が多い場合は、家庭裁判所に相続放棄の申請をすれば相続人が夫妻を引きつがなくても良くなります。
当事務所で、アドバイスや申請書類の作成、必要書類の取得、を代行します。
LⅠN E 公式アカウントからもお問合せいただけます
LINEを使ってのお問合せも可能です。電話をする時間が中々作れないという方は是非ご活用ください。
↓↓友達登録はこちら↓↓