遺言書の内容を確認する
遺言書が見つかったら、その内容を確認してみましょう。遺言書は書き方だけでなく内容についても法律で細かく決められています。遺言書に書いてあれば、なんでもかんでも従わなければいけないわけではありません。遺言によって法律的に効力があるのは、一般的に次のような場合です。
相続方法について確認する
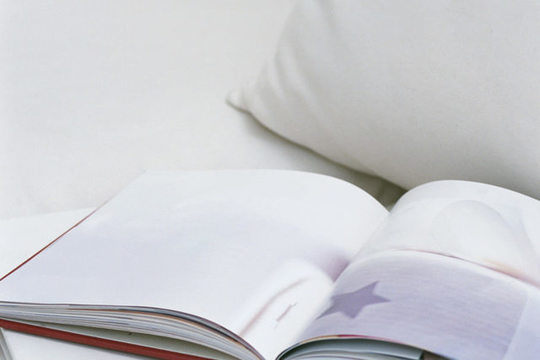
遺言書に記載されている、誰がどのような財産を相続するのか、という指示を確認します。
民法では、遺言書でできる相続の指定方法について限定的に次のような事ができる、と定めています。
①推定相続人の廃除、廃除の取り消し
②祖先の祭祀主宰者の指定
③相続分の指定
「〇〇は相続分3分の2を、〇〇は3分の1を相続する」などという指定です。
④特別受益の持戻しの免除
生前に受けた贈与について、相続分に影響を受けないこととする指定です。
⑤遺産分割方法の指定
何分の何といった割合を指定するのではなくて、「〇〇は自宅不動産を、〇〇は預貯金〇〇円を相続する」などと、財産を個別個別に指定する方法です。
⑥遺産分割の禁止
⑦遺産分割における担保責任に関する別段の定め
⑧遺贈の減殺方法に関する別段の意思表示
例えば、もし遺言者に奥さんがいなくて、相続人が子供ふたりだけだったとします。この場合、もし民法で決められた通りに相続する場合は、それぞれ2分の1ずつ相続するというのが原則です。
しかし、もし遺言を残している場合は、この規定通りではない相続方法を指定する事が出来ます。
遺贈、寄付などを確認する

遺言においては、そもそも相続人ではない人に財産を与える事も出来ます。
遺言書にて他人に財産を譲る事を遺贈と言います。
遺贈の場合は相続と違って、租税が多かったり、不動産の名義変更手続き方法が異なったりします。
また、財団法人をつくる寄付行為や信託の設定をすることも出来ます。
認知、後見人の指定などを確認する

認知とは、婚姻外の子供を自分に関して、男性が自分の子供だという事を認めて戸籍上、正式な親子として成立させる事です。
もし認知をした場合、認知された子は当然に相続人となるため、遺産を譲り受ける権利を得ます。
結婚していない女性との間に子供がいて、生前に認知していなかった場合は、遺言書にて認知をする意思表示をする事で、自分の子供として認める事が出来ます。
遺言執行者について確認する
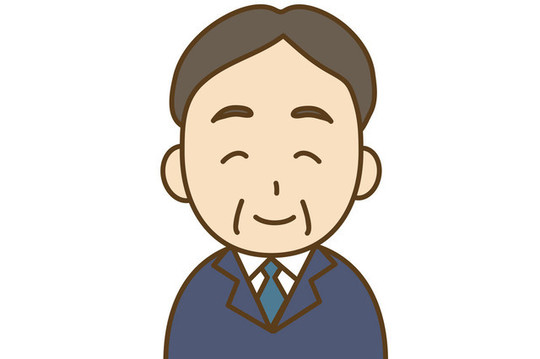
遺言執行者とは、遺言書に書いてある内容の手続きを実際に行う人の事です。
遺言を各段階で適任者がいない場合は、遺言執行者を誰にするか決める人を指定出来ます。
遺言執行者について詳しくはこちら
法律で定められていない内容については効力がない

上記のように、遺言で指定する事ができる内容以外のものは、法律的にはなんの拘束力もないものになります。
冷たい言い方をすると、単なるお願いでしかなく、相続人たちはそれに従う義務もありません。
例えば、「葬儀は密葬にして欲しい」とか「〇〇さんに、伝言をして欲しい」などは法律上なんの効力もないのです。
しかし、法律で定められていないとしても、故人の生前の思いが詰まった内容であるので、最大限尊重してあげたいと思います。
LⅠN E 公式アカウントからもお問合せいただけます
LINEを使ってのお問合せも可能です。電話をする時間が中々作れないという方は是非ご活用ください。
↓↓友達登録はこちら↓↓