自筆証書遺言の保管制度
自筆証書遺言保管制度は、遺言者が作成した自筆証書遺言を法務局で安全に保管できる制度です。紛失や改ざんの防止、家庭裁判所での検認が不要になるといったメリットがありますが、遺言の内容が法的に有効かどうかまでは確認されません。
このページでは、自筆証書遺言保管制度についてご案内致します。
目次
- 自筆証書遺言保管制度とは?
- 申請手続きについて
- 保管後の流れ
- メリット・デメリット
- 公正証書遺言との違い
- まとめ
1.遺言書を書いたけれど、どこに保管すればいい?
「自筆証書遺言保管制度」とは?
将来、家族が相続をめぐって争わないようにと思い、せっかく「自筆証書遺言」を作成したものの、「この遺言書をどこに保管すれば安全なのだろう?」と不安になる方も多いのではないでしょうか。
- 遺言者本人が、時間の経過とともに保管場所を忘れてしまう
- 相続人等が遺言書の存在に気づかず、発見できない
- 家族の誰かが意図的に遺言書を隠したり、内容を改ざんする
- 火災や地震、水害などの災害によって、遺言書が紛失したり破損してしまう
こうした事態を防ぐために、「自筆証書遺言保管制度」という制度ができました。
この制度を利用すると、自分で書いた遺言書を法務局に預けることができ、その内容が安全に保管されるだけでなく、後に相続人等へ伝えられる仕組みが整っています。
保管制度のメリット!
- データは死亡後150年保管されるので紛失防止・偽造防止になる
- 裁判所による検認手続きが不要
- 相続開始後に、あらかじめ遺言者が指定した人に通知が届く
- 相続開始後に、全国どこの法務局でも相続人等が遺言書の有無を確認できる
- 公証役場で作成する公正証書遺言より費用が安い
2.申請手続きについて
申請者
自筆証書遺言を作成した本人が申請します。
※本人が必ず直接出向く必要があり、代理人による申請や郵送による申請はできません。
申請先
次のいずれかの法務局(遺言書保管所)になります。
- 遺言者の住所地を管轄する法務局
- 遺言者の本籍地を管轄する法務局
- 遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局
必要書類
- 遺言書
- 保管申請書
- 住民票(本籍・筆頭者が記載されているもの。マイナンバーなしの原本)
- 本人確認書類(顔写真付きで有効期限内のもの)
- 手数料(3,900円分の収入印紙)
申請の流れ
自筆証書遺言を作成する
申請書や必要書類を準備する
管轄の法務局へ申請の予約をする
※法務局手続案内予約サービスの専用サイトで24時間いつでも予約可能です。
または電話や窓口で予約をします。
予約日に法務局へ出向く
手続きが完了すると「保管証」が発行される
保管される遺言書の条件(様式)
- 左側20mm、上・右5mm、下10mmの余白があること
- 文字が判読できる大きさ(4号サイズ)で片面のみ書かれていること
- 各ページにページ番号があること
- ホチキスなどで綴じていないこと(データ化のため)
3.保管後の流れ
遺言者の生前にできること
変更の届出
遺言者の氏名、生年月日、住所、本籍(または国籍)、筆頭者、および遺言書に記載された受遺者・遺言執行者等の氏名または住所に変更があった場合は、速やかに変更の届出をする必要があります。
- 申請者
遺言者、遺言者の親権者や成年後見人等の法定代理人
- 申請先
全国の遺言書保管所。郵送可。
- 必要書類
届出書、変更を証する書面(住民票の写し、戸籍謄本等)、本人確認書類等
なお手数料は不要になります。
保管申請の撤回
遺言者本人は、自身の遺言書の保管をやめたい場合、保管されている遺言書保管所に申請の撤回を行い、遺言書の返還を受けることができます。この撤回は遺言の効力には影響しません。
- 申請者
遺言者本人のみ
- 申請先
原本が保管されている遺言書保管所のみ。郵送不可。
- 必要書類
撤回書、写真付き身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
氏名・住所等が変更されていて、変更届をしていない場合はそれを証明する書類
なお手数料は不要になります。
遺言書の閲覧
遺言者本人は、自分の遺言書を確認したい場合、遺言書保管所に閲覧を請求できます。
- 申請者
遺言者のみ
- 申請先
原本の閲覧:原本が保管されている遺言書保管所
データ(モニター)閲覧:全国の遺言書保管所
- 必要書類
閲覧請求書、写真付き身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 手数料
モニター閲覧:1回につき、1,400円
原本閲覧:1回につき、1,700円
遺言者が亡くなったあとにできること
遺言書保管事実証明書の交付請求
遺言書が保管されているかどうかを確認するための証明書の取得を請求できます。保管されていない場合もその旨の証明書が発行されます。
- 請求者
相続人、受遺者・遺言執行者など
上記の法定代理人(親権者・後見人など)
- 請求先
全国の遺言書保管所。郵送可。
- 必要書類
交付請求書・遺言者が死亡したことを確認できる書類(※除籍謄本、関係遺言書保管通知又は指定者通知等)・請求者の住民票
※請求者によって更に必要となる書類があります。(相続人であれば相続人であることが分かる戸籍謄本等)
- 手数料
1通につき、800円
遺言書情報証明書の交付請求
遺言書の画像情報すべてが記載された証明書の取得を請求できます。原本は法務局に保管され遺言者が撤回しない限り返却されませんので、遺言者死亡後にはこの証明書を取得することで相続手続きを行うことになります。
この証明書は家庭裁判所での検認が不要なものになります。
- 請求者
相続人、受遺者・遺言執行者など
上記の法定代理人
- 請求先
全国の遺言書保管所。郵送可。
- 必要書類
交付請求書
法定相続証明情報もしくは遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本及び相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の住民票の写し
※兄弟姉妹が相続人になる場合など、相続人によって必要な戸籍の範囲が変わるので注意が必要です。※請求者によって更に必要となる書類があります。
- 手数料
1通につき、1,400円
遺言書の閲覧
遺言書の内容を直接確認したい場合には、原本かデータ(モニター)の閲覧をすることができます。この閲覧請求をすると、遺言書保管官は、その方以外の全ての相続人等に対して、関係する遺言書を保管している旨を通知することになります。
- 請求者
相続人、受遺者・遺言執行者など、上記の法定代理人
- 請求先
原本の閲覧:原本が保管されている遺言書保管所
データ(モニター)閲覧:全国の遺言書保管所
- 必要書類
閲覧請求書、法定相続証明情報もしくは遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本及び相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の住民票の写し
※兄弟姉妹が相続人になる場合など、相続人によって必要な戸籍の範囲が変わるので注意が必要です。また相続人以外が請求する場合も別途必要な書類があるので確認が必要です。
- 手数料
モニター閲覧:1回につき、1,400円
原本閲覧:1回につき、1,700円
遺言者が亡くなって自動で相続人や受遺者に通知がされる方法
遺言者が遺言書保管所に遺言書を預けていることを一切誰にも伝えていない場合、相続人や受遺者は気付かないままになる可能性があります。
そこで通知される方法として2種類があります。
1.指定者通知
法務局の法務事務担当者(遺言書保管官)が遺言者の死亡の事実を確認した場合に、あらかじめ遺言者が指定した人(3名まで指定可)に対して、遺言書が保管されている旨を知らせるものです。この通知は、遺言者が希望する場合に限り実施します。遺言書の画像情報すべてが記載された証明書の取得を請求できます。原本は法務局に保管され遺言者が撤回しない限り返却されませんので、遺言者死亡後にはこの証明書を取得することで相続手続きを行うことになります。
この証明書は家庭裁判所での検認が不要なものになります。
2.関係遺言書保管通知
遺言書保管所に保管されている遺言書について、遺言者の死亡後に、関係相続人等が、「遺言書の閲覧」や「遺言書情報証明書の交付請求」をした場合に全ての関係相続人等に対して、遺言書保管官が、遺言書保管所に遺言が保管されていることを知らせる仕組みです。遺言書の内容を直接確認したい場合には、原本かデータ(モニター)の閲覧をすることができます。この閲覧請求をすると、遺言書保管官は、その方以外の全ての相続人等に対して、関係する遺言書を保管している旨を通知することになります。
4.メリットとデメリット
遺言書保管所において、遺言書は原本は死亡日から50年、データは150年は保管されることになるので紛失防止・偽造防止には非常に有効です。
保管申請がされると、遺言保管官は遺言が民法968条の方式に適合しているかを確認することになります。日付や署名・押印等の形式的要件について審査しますが、内容について審査するわけではありません。また、遺言書が真正に成立したと推定さるものではありません。そのため、相続発生後の家庭裁判所の検認は不要になりますが、実際の手続きで利用できるのか等の中身の判断はされません。
5.公正証書遺言との違い
公正証書遺言は、遺言者が遺言の内容を公証人に伝え、公証人が作成する方式の遺言です。作成時に公証人が関与することで、方式不備を回避することができます。
また、内容についても確認することになるので、後に無効とされるリスクは少ないものとなります。
自筆証書遺言保管制度を利用しても検認は不要になりますが、内容までは担保されるものではないので実際の相続手続きで無効と判断される可能性があるものとなります。
なお、公正証書遺言は作成費用が自筆証書遺言より高めであることと、遺言の内容についても検討するものになるので自筆証書遺言よりは時間がかかるものとなります。
6.まとめ
自筆証書遺言保管制度は検認不要で安全に保管できますが、内容の有効性まで担保されません。費用や手間はかかりますが、公正証書遺言のほうが実際の相続手続きで使える可能性が高いものになります。ただし、今後内容を変更する可能性がある場合などは公正証書遺言だと再作成費用がかかるため、ひとまず偽造防止等で保管申請をすることは有効であると思われます。自身の状況や何を重視するかを考えて、望ましい手続きを選ぶことになります。
当事務所の相続相談のご案内
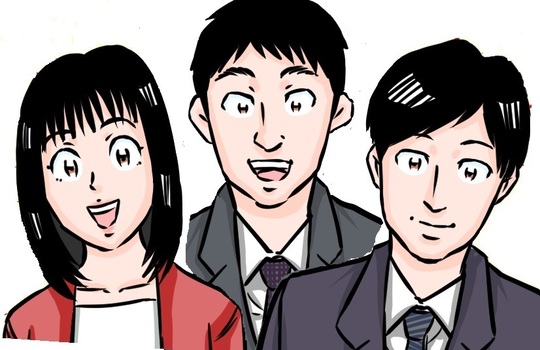
当事務所では、相続手続きにお困りの方を対象に、全ておまかせ頂けるお役立ちプランを用意しています。
《次のような方はお気軽にお問合せください》
- 相続についてなにか始めれば良いかわからない。
- どこに頼んで良いかわからない。
- 遺産分割をどうすすめてよいか相談したい。
- 忙しくて自分で手続きが出来ない。
不動産から預金、株までほとんどの手続きを
まるごとおまかせ
当事務所の相続おまかせプランなら、ほとんどの相続手続を司法書士が代わりに行います。不動産だけ、とか預金だけ、とバラバラに頼むことなく、全ての手続きを一括して頼めるのでとても楽に進めることが出来ます。
低価格でのサービス提供
相続おまかせプランは基本料金22万円からのパックとなっております。他の事務所や信託銀行などと比べてもとても安い料金設定です。
《相続財産が5000万円の場合の料金比較》
| A信託銀行 | B行政書士事務所 | C司法書士事務所 | 当事務所の 相続おまかせプラン | |
| 料金 | 110万円~ | 49万円~ | 70万円~ | 22万円 |
頼みやすく敷居がひくい
司法書士や税理士などは、なんとなく堅苦しくて頼みづらい、というイメージを持っていらっしゃる方は少なくあります。
当事務所では、なるべく皆様にお気軽に問い合わせをしてもらえるよう、最初のお電話から、わかりやすく親切にをモットーに対応をしております。
初回無料相談のご予約はこちら
品川大田相続相談センターのホームページにお越しいただき、ありがとうございます。当サイトの正式な事務所名は市民の森司法書士事務所と言います。お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。

お気軽にお問合せください
よくあるご質問
- 初めての相続で、どうして良いかわかりません・・
- 相続手続の費用は大体いくらかかりますか?
- 相続の知識は全くないですが大丈夫ですか?
- 遺産分割で親族がもめるのではないかと心配です
- 公正証書、自筆証書など遺言の違いを知りたいです
どのようなお悩みのご相談でも結構です。
お悩みの方はご相談をお待ちしております。
受付時間:10:00〜19:00
土日祝日のご相談に関しては、トップページで休日相談日をご確認ください。
当事務所のお手伝い
不動産、銀行、株など、あらゆる相続のお手続きを当事務所が代行いたします。
遺産分割協議書の作成から財産の名義変更など、おまかせください。
一番多く、お申し込みがある
お手伝い内容になります。
残された財産よりも借金の方が多い場合は、家庭裁判所に相続放棄の申請をすれば相続人が夫妻を引きつがなくても良くなります。
当事務所で、アドバイスや申請書類の作成、必要書類の取得、を代行します。
LⅠN E 公式アカウントからもお問合せいただけます
LINEを使ってのお問合せも可能です。電話をする時間が中々作れないという方は是非ご活用ください。
↓↓友達登録はこちら↓↓







